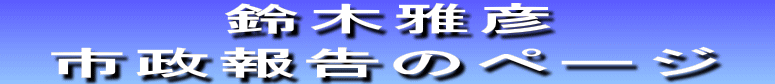
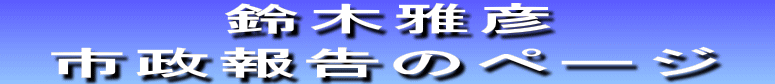
| �g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@���[���@�@ |
| ���E�Ǝs���Ɋւ�鏔��� |
| ������� | �s���l���� | �S�~�����ꎋ�@ | ���������y�� |
| �A�����M�[�Ή����H | �x�̖h�Б̐� | �����{���ւ� | ������̌����� |
| �X�H���̍� | ���h�E�����s�� | �����R�̌����g�� | �Îs�E�����i�� |
| �����Ґ����� | �u�o�ΐ쐅�Q�� | ���֏��� | |
| �]�ˋ��w�����֏���ڂ����@������ݒu���邩 09.12.30 |
| �@�ߓS�]�ˋ��w�̐��H�̐����ɁA���]�Ԃ̒��֏ꂪ����܂��B�����ɂ́u�]�ˋ��w���������]�Ԓ��֏�v�ƌ����܂��B���ꂪ�]�ˋ��w���ӂ̌�ʂ̍����̈�����Ǝw�E���鐺����������܂��B �@�ƌ����̂��A�������瓥��n��A���]�Ԃ��߂āA�ēx�A����n���ē����ɖ߂��Ă���łȂ��ƁA�]�ˋ��w��O�d��w�ɍs���Ȃ�����ł��B�w����k���ŁA���邢�͎���玩�]�Ԃł���ė����l�������A�����ԂƑ����Ȃ��瓥��n����i���A�ʋΒʊw���ɌJ��Ԃ���Ă��邩��ł��B �@�l�����]�Ԃ������Ԃ��A���͎��ԂƂ̐킢�ŋ}���ł��܂��B���݂����v�����]�T������܂���A���̂����Ă��鎞�ԓ��ɁA���]�Ԃ������Ԃ̑O������A�����Ԃ��l�������̂���悤�ɂ��ēn�炴��Ȃ��̂ł��B����ł͂��厖�̂��N���邩�ƁA�n���̕��X���S�z����̂����R�ł��B �@���̉�����Ƃ��ẮA�]�ˋ��w�ɐ�������邩�A���֏�𓌑��Ɉڐ݂��邵������܂���B�\����̖��ł�����A��ʃ��[�����������Ƃ���ʼn��̉����ɂ��Ȃ�܂���B���ł̎��̂͑�S���ɂȂ肩�˂܂���B�a���������邱�ƂƁA��ʈ��S�̂��߂ɁA���̖����������ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �u�o�ΐ�̐��Q��ɘN�� 09.12.28 |
| �@�O�d�����͐�̐����v���R�c���Ă��܂��B���̒��ɂ͎u�o�ΐ�̐��Q����܂܂�Ă���A�����I�ɂ�200�N�ɂP�x�̍^���ɂ��Ή��ł���悤�Ȍv��𗧂Ă悤�Ƃ��Ă��܂��B �@�u�o�ΐ�͐��������邱�ƂƓ����ɁA�앝�������Ȃ��Ă��镔���̊g�����d�v�ۑ�ƂȂ��Ă���A����10�N�O�ɏ����I����������A���̂��Ƃ����߂Ă��܂����B���ݐR�c����Ă���Ƃ���ł́A�u�o�ΐ�͌�����ߓS�̓S�������܂ł�D���ԂƂ���\��ŁA�앝�̋����Ȃ��Ă��鍑���ɉ˂���V�]�ˋ��ƍ����ɏo�邽�߂̍]�ˋ��A�����ċߓS�S���������g�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B �@�앝���L����Ƌ����˂��ւ��Ȃ���Ȃ�܂��A���Ƃ��Ύs���ł���]�ˋ��̊|���ւ��͒Îs�̐ӔC�ŁA2015�N���Ɋ����Ɨ\�z����Ă��܂��B �@���������v���2010�N�Q���Ɍ��Ă����肳���\��ł��B�v�悪���s�����ƁA�u�o�ΐ�ɗR�����鐅�Q�ɋ����ĕ�炷�悤�Ȃ��Ƃ͊�{�I�ɉ����������̂Ɗ��҂���܂��B |
| �����Ґ����� 09.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�����A�s�c�I�̗����\��҂̐�����ɁA�ȂƎ������̂R�l�ōs���Ă��܂����B�ЂƂ̊��ɂ͂ЂƂ̐w�c���w����Ă��܂�����A�����Ă݂��43�w�c�������Ǝv���܂��B�l�̓��Ō����ɂ����ꏊ������̂ŁA�m���ł͂���܂��A�\�z�ʂ�̐��ł��B �@���E�c���͎��ȊO�ɂ́A�V�l�w�c�̂��߂ɗ����Ǝv�����������l�A���Ƃ͌㉇��̕��X���唼�ł����B�唼�Ƃ����̂́A�V�l���҂̊炪���l������܂����̂ŁB �@�A��ہA�`���b�Ǝ��E�ɓ����������̉���Ɍ��o��������܂����B�A���b�A�l�Ⴂ���Ȃ��A���̐l������ȏ��ɂ���͂����Ȃ��A�Ǝv���Ă���ƁA���̏������������܂��B�����āu�o���Ă��܂����v�ƌ����ł͂���܂��B��͂�v���Ă����ʂ�̏����ŁA�鍑�f�[�^�o���N�Ŏ����̃A���o�C�g�����Ă��������ł����B �@���ׂ̗ɂ́A���ҁB���A�����Ă݂�A�킪�Ƃ���Q�Ԗڂɋ߂��Ƃ���ɏZ��ł�����҂ł����B����A�r�b�N�����܂����B������̓X�[�p�[�Ńo�b�^��������đI���𗊂��Ƃ��������͂��ł����A���҂̉�����Ƃ́A����͂�B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22�N�x�̗p�̒Îs�E�����i�Ґ��ꗗ 09.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����R�̌����g���ɖ��邢�W�] 09.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@12���c��Ō����R��ʂ錧�����A�Ð��n�C�^�E��������̐M���̂��i�O�d�������ƒ{�ی��q�����O�j�ŋ����Ȃ��Ă���������グ�A�g�������߂鎿������܂����B����ɑ��A���ǂ���͔��ɑO�����̓��ق�����܂����B���ق̗v�|�͈ȉ��̒ʂ�ł��B �y���ق̗v�|�z�@�s�̐\������ɂ�苷襕��̂Q���̒n���҂Ǝs�E���Ƃ̋��c�ɐi�W������A���Ƃɑ�����̗�������������B���ʂ̂��߂̗���������������Ă����������B�����ɍ��ӂ����������Ċg����}�肽���B �@�܂�A�ڍ����Ă����n�傳��Ƃ̘b���������ĊJ����A���ʂ̂��߂ɒn�傳��̓y�n�ɓ��邱�Ƃ̋����Ղ����A���Ă͑����ɉ�����}�肽���A�Ƃ����킯�ł��B �@�����ŁA�u���p�҂ɂƂ��Ă͖��邢�W�]���J�����ƍl���Ă������̂��v�ƍĊm�F�����߂�ƁA�u�b�������ɉ����Ă��炦�Ȃ�����������l����A���邢�W�]���J�����ƌ�����v�Ƃ̓��ق��Ԃ��Ă��܂����B�ܘ_�A���ꂩ��b���������X�ɏd�˂���킯�ł�����A����Ŗ��S�Ƃ����킯�ɂ͂����܂��A�g���͌����I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����Ƃ͌�����ł��傤�B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���h�E�������|�I�ɑ���܂��� 09.12.11 |
| �@12���c��̎��^�̒��ŁA���h�͂Ɋւ�����̂�����܂����B���̎w�j�ɂ��A�Îs�ŕK�v�Ƃ������h�E���̐���583���A����ɑ��āA���ۂ̏[������60�������Ȃ��Ƃ������قł����B���̂��Ǝ��̂́A���������I����10�N�O�Ɏ��₵�����Ƃ�����A�����͍����O�ł����琔���͈Ⴂ�܂����A�[�������Ⴂ���Ƃ͏��m���Ă��܂����B �@���قɂ��ƑS���̕��Ϗ[������75.5���ł��B�S���̕��ς����傫��������Ă��܂��B�������c��ŐE���������炷���Ƃɍ��ӂ����̂ł����A���̎��ɒ�Ă��ꂽ�̂��A�ގ��c�̂Ƃ̔�r�Ȃǂ�2800�l�ɂ���Ƃ������̂ł����B�Ƃ��낪�A�����͍ő�̍s�v�Ƃ����|�����̌��A���|�Z�����́u�����ꐺ�v�݂����Ȃ����̒��ŁA����ɂP���팸���邱�ƂɂȂ�A2500�l�̐��Ɍ����Ă̍팸���n�܂����̂ł��B �@�]���āA2500�l�Ƃ��������ɂ͍����͂Ȃ��Ɠ��ǂ��ψ���ł̎��̎���ɑ��ē��ق��Ă���̂ł����A��U���߂����Ƃ̏C���������Ȃ��̂��d���������s���̈������ŁA�������Ȃ��ƌ����Ȃ���2500�l�Ɍ����ĐE�������炵�����Ă��܂��B���̂������H���āA���h�E���̏[�������S�����ς��ꡂ��Ɉ������̂ɂȂ��Ă���̂ł��B �@�~�}�̂��炢�����ɂȂ�A��n�k�����N���Ă����������Ȃ��Ƃ������ɁA2500�l�̐��ɂ����݂����Ƃ��s���ɂƂ��čK���Ȃ��Ƃł��傤���B600�l�߂��K�v���Ƃ����̂ɁA350�l�������Ȃ����Ƃ̏d��ȈӖ��������ƔF������K�v������܂��B�Z���^�[�p���X�ɂR���~���̉ƒ������炢�Ȃ�A�K�v�ȕ����̐E���͂�����Ɗm�ۂ���ׂ����ƍl����̂�������O�ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �X�H���̍����ܑ��������Ă����� 09.11.03 |
| �@��������Ă���Ɛ����ŊX�H���̍������肾���āA�����ܑ̕��������Đ���オ���Ă��鏊���ڂɕt���܂��B���̖��ɂ��ĕ����̕����炲�w�E���܂����B�����̕������̎����ɋC�����Ă����邱�ƂƎv���܂��B �@�������A�X�t�@���g�ܑ��̏ꍇ�͒P���Ɋ���Đ���オ���Ă��܂����A�J���[�u���b�N����ׂ��ܑ��ł��ƁA�J���[�u���b�N�������オ���Ă��܂��B�����ău���b�N���Ƃɕ����オ������Ⴆ�A�X�̊p�x���Ⴂ�܂��B�����ɂ������Ƃ͖��炩�ł��B �@���𐢑�ł������ł�����A���̏オ��������Ȃ��Ȃ鍂��҂�A�Ԃ����̕��ɂƂ��Ă͑����[���Ȗ��ł��B�ꏊ�ɂ���Ă͎��]�Ԃł̒ʍs���s�\�Ȃ��炢����オ�肪�A�����Ă��鏊������܂��B�x�r�[�J�[�ł̎U���ɂ�����܂����A����҂̎艟���Ԃ������������ē�a���Ă��܂��B �@���̖����ǂ����������炢���̂��A�����ɂ͖��Ă������т܂��A�Îs�̌��ݕ��ɂ͑��k���܂����B�����ɉ�����i���o�邩�ǂ����͕�����܂��A�Îs�ɂ͓��H�Ǘ��̐ӔC������܂��̂ŁA�S���̎�����������āA���Ђ悢���@�������Ă������������Ǝv���܂��B |
| �J�@���@�Ɓ@�@�� 09.11.21 | ||
| �@���̎ʐ^�͈�g�c�ɂقNj߂��c�n�ɗאڂ��čL���镗�i�ł��B�c�ނߗ��ĂĊJ�����i�̂ł����A�߂������ȁA�r���ŊJ�����X�g�b�v�����܂܁A���u����Ă��܂��B�c�ނƎR�̕��i���L����A�̂ǂ��ȕ��͋C�������̂ł����A����A���S�Ƃ��������悤������܂���B �@�ߏ��̕��Ɂu�Îs���J�������o������ł���v�ƌ����A�Ƃ��Ă��h���v�������܂����B �@�J���Ɗ��A���̃o�����X�������Ɏ�邩�A�����̂����́u�N�w�v�������A������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����オ���Ă��܂��B
|
| �c����v������̂����������K�v�H 09.11.18 |
| �@�Îs�c��ł͒萔���̌�����Ɉ��������āA�c����v�̌�����s���Ă��܂��B�萔���ɂ����ẮA������̏��̔C�����I�����Ȃ����ɁA�����������̌����s���Ȃ��܂܁A�萔�팸�̌��_���o���A�c����Ăŏ���ς��Ă��܂��܂����B������ʂ����������ꌩ����I�Ɍ����Ȃ���A���_�������o�������ɍ������������Ȃ��������Ƃ��C�ɂȂ��Ă��܂��B �@�c����v�̌�����������ł��B�C���I���܂Ŕ��N�Ƃ��������ɁA������̋c��Ƃ��āA�����Ď��̋c����\��������X�郋�[�����ɍڂ���̂͂������Ȃ��̂��ƁA���͊����Ă��܂��B���ɉ���c���d�ˁA���[���Â���͎ϋl�܂����܂��B�����Ă��̃��[���ɔ�����͎̂��������E�c���ł͂Ȃ��A���̋c����\������c���̊F����ł��B �@�{���I�Ɍ����A���̋c��̂��Ƃ́A���̋c����\��������X�ɔC����ׂ��؍����̂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�萔���������ł��B������̔C�����I�����A���̋c����\��������X���A�����̌������钆�ŁA�S�N�̔C���̑��������ɒ萔�ɂ��Č��_���o���ׂ��؍����̂��̂������Ǝ��͍l���Ă��܂��B �@���������Ӗ��ł́A���݂̋c��͏������}�ɉ߂��܂����A���̋c��ɑ��ęG�z�ȍs�ׂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����O���܂��B�c����v������̂�����ɂ��Ă̌�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA������ۂ��v���������Ȃ�܂��B���ɂ��Ă��A���v�͋}���ׂ��ł͂Ȃ��A�T�d�ɍs�����Ƃ������̔錍���낤�Ǝv���܂��B |
| �s�������{���đւ��E�V�v��Ă\ 09.11.14 |
| �@����̑S�����c��̈Č��̂ЂƂɁA�����{�݂̗����p�Ă�����܂����B�ϐk���x�̖��Ȃǂ��猚�đւ��̕K�v�ȑ����x����s�������̌��c�Z��Ւn�E�Ìx�@�Ւn�̗��p�ĂȂǂ�����܂����B����ɂ��Έ��Z�ƌ|�Z�����������x���̌��đւ����K�v�Ƃ���Ă��܂��B �@�������s�v�c�Ȃ̂́A�ȑO�Ɏ����ꂽ�����{�݂̗����p�̕������ł́A�e�����x���̎d����{���ɏW�A�x���@�\���k������̂������p�v��̒��S�������͂��Ȃ̂ł����A����ɂ��Ă͈ꌾ���G����Ă��܂���B��́A���̊Ԃɒ��g������ւ���ꂽ�̂ł��傤���B �@���قɂ��A���̓��e�̕����ōŏI���܂Ƃ߂�Ƃ̂��Ƃł����A����ł͗����p�v��ł͂Ȃ��A�V���Ȍ����{�݂̌��v�悻�̂��̂ł��B�Ȃ��x���ꂽ�C���ł��B �@���X�͊e�����x���ɋX�y�[�X������Ȃ���A�R���~���̉ƒ����Ĉꕔ�̕������Z���^�[�p���X�ɓ������Ă��閵�����������邽�߂ɁA�����p�v�悪�o�Ă����Ɨ������Ă���̂ł����A����ɂ��Ă͑S���G����Ă��Ȃ��v��ĂɂȂ��Ă��܂��B �@�V�̑����x���ƂQ�̌����{�݁A�{���ɗ��̒��ԏ��V���Ɍ��݂���̂ł�����A���\���~������̂�������Ă��܂��A�������������������ƌ����Ȃ���A���͌������Ȃ����Ƃ�\���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Z���^�[�p���X�̒Îs�g�p�������������������ۂLj��オ�肾�Ƃ̈ӌ����o�܂������A������ł���Ȃ�A���̕�����͍�����Ǝv���̂ł��B�Z���^�[�p���X�������̈ꏕ�ɂ��Ȃ�킯�ł�����B �@�Ȃ�ɂ��Ă����z�̐ŋ��̓����A�傫�Ȏ؋��������b�ł�����A�s�c�I�̑��_�̂ЂƂɂȂ肻���ł��B |
| �\���J�x�̌x���̐��͂���ł����̂��@09.10.08 | |
| �@�䕗�̎��͂��������Ȃ̂ł����A�P��ɂ��P���Ԕ�����Q���ԁA��ӂɂQ��A���H���������₷�����Ȃǂ�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�����������������ĉ��܂����B�ŏ��̌����̎��A��g�c�o�����Ɋ��܂����B�����ɑҋ@���Ă����͈̂�l�B�O�ɏo�Ă���̂��ȂƎv���A�u���̕��X���ҋ@���Ă����ł���H�v�Ɖ��C�Ȃ��q�˂܂����B �@����ƁA�u���₠�A����l�Ȃ�ł���v�u�����H�v�u���N���炱���Ə��w�Z�̂Q�����łR�l�̑̐��ɂȂ�܂��āv �@�o�����ɂ͏Z�����炢�ǂ�ȓd�b���|�����Ă��邩������܂��A�Q�K�̌����قɔ��悤�Ƃ���ė���l�����܂�����A��킯�ɂ͂����܂���B�Ƃ������Ƃ́A�Z�����炱�����댯�����猩�ė~�����ƌ����Ă��Ή��ł��Ȃ��ƌ������Ƃł��B�R�l�̓��̈�l���Ή������Ƃ��Ă��A��������Ŏ��t�ł���ȏ�̗v�]�ɂ͉������܂���B �@����Ŏs���̖��ƍ��Y����邱�Ƃ��ł���ł��傤���B�s�����������邱�Ƃ���ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���S�E���S�v�̊X�Â���Ƃ͌������ꂽ�x���̐����ƌ��킴��܂���B�̐��̌����������߂Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����A�T�������猩���������͈͂ł́A�K���X�̊��ꂽ�Ƃ��P���A�A���e�i�̓|�ꂽ�Ƃ��Q���A���̑��A�y�ǂ̈ꕔ�������ꂽ�Ƃ͐��m�ꂸ�B�܂��A�����̔��A���E�v�����^�[����������|��Ă��܂����̂ŋN�����Ă����܂����B����ɂ��Ă��䕗��߂Ƃ͂������A���̏u�Ԃ��Ăт��Ȃ�̉J�ƕ��ɂȂ��Ă��܂��B �@���̌����̎��ɎB�����ʐ^�����Ɍf�ڂ��܂��B |
|
| �����ƑS�� ���ʂ̈Ⴄ�і���  |
����������̖і��� |
����܂Ő��̂Ȃ������c�ނ��E�E�E |
�����������ʂ�������� �r��������t���ł�  |
| ���̐��H�͕��i�Ȃ� �����������Ő��������܂���  |
�Z����Q�̑�����g�c�ł� �y�X���������܂���  |
| ���H�Z���^�[�̌����_�ł̔z�u�} �A�����M�[�Ή��s�\�ł͂Ȃ����@09.08.06 |
|||
| �@���w�Z���H�����ׂĂ̒��w�Z�Ŏ��{���邽�߂ɁA�Îs�͋v���̍H�ƒc�n�ɋ��H�Z���^�[�����݂��A����23�N�x���狋�H�������J�n���܂��B���̂��߂ɂU��19���A���A�[���E�A�C�E�G�[���É��x�ЂƐv�Ɩ��ϑ��̌_������킵�܂����B�c��ɑ��ẮA��������ψ���̋��c��œ��e��������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���̂��߂̎��������ɋc���̎茳�ɓ͂��Ă��܂��B �@���̎����ɂ́A�u��{�v�̒��ƂȂ錻���_�ł̔z�u�}�v���Y�t����Ă��܂��B���̒��ɂP�K���ʐ}������܂��B���̕��ʐ}�ŋC�ɂȂ�̂��A�u�A�����M�[���ʎ��v�ł��B�܂�H���A�����M�[�̐��k�ɑΉ��������H�����邽�߂̕����ł����A�P�K�̐^�ɂ���܂��B����ŃA�����M�[�ɑΉ��ł���̂ł��傤���B �@�A�����M�[�̌����ɂȂ�H�ނ͉���ނ�����A�ǂ̐H�ނɃA�����M�[�Ǐo�邩�́A���k��l��l�Ⴂ�܂��B�]���āA�Z���^�[���ł̐H�ނ̓����A�����������Ȃ��悤�ɂ���̂���{�ł��B�Z���^�[�̐^�ɐݒu���đ��v�Ȃ̂ł��傤���B�����Ĉꎺ��������܂��A����ő��v�ł��傤���B�����A���Ε��A���A�����A�G�r�A�J�j�A�C�J�A�I�A�i�b�c�ނȂǂȂǁA�{���ɑ��푽�l�ȃA�����M�[�ɑΉ������������P���ʼn\�Ȃ̂ł��傤���B �@�{���A��������H����A�����M�[���Ƃɕ�����ׂ��Ȃ̂ł�����A�ЂƂ̕����ʼn��\�H���̈قȂ�A�����M�[�Ή����H����邱�Ƃ́A�����I�ɕs�\�Ȃ͂��ł��B���ɋ��H�Z���^�[�ɓ��ʐH��������݂�������ǂ������I�ɂ͑Ή����s�\�������̂ŁA���ʐH���������g���Ă��Ȃ��A�A�����M�[�̐��k�ɂ͉ƒ납��ٓ̕����Q�őΉ����Ă�����Ă���Ƃ��������̂�����̂ł��B �@���H���ԂŔz�V�̎��Ɏ�ɕt���������ŃA�����M�[�Ǐo��ꍇ������܂��B����Ȃ̂ɃZ���^�[�̐^�ɂP�������A����ł͋t�ɃZ���^�[�̋��H�ŃA�����M�[�������N�����\�����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| ���������y�����P�N�łP���㏸�Ƃ̕�����܂����@09.06.27 |
| �@����A�����������畽��20�N�x���ɂ����鉺�����̕��y�ɂ��Ă̕����͂��܂����B���̂P�N�Ԃŕ��y���͂P���A�b�v�����Ƃ̂��Ƃł��B �@�Ȃ��A�Îs�͔_�ƏW���r���⍇�����������������ƔF�߂Ă��܂���̂ŁA��ʂ̊��o�ʼn����Ǝv�����̂́u���������v�ƌĂ�ł���A���̕��y���͉��̕\�ɂ���悤�ɁA76.7���ɂȂ�܂��B������41.1�����u�������v�ɂ�鏈�����ƌ������Ƃł��B |
| �N�@�x | �Á@�s | �O�d�� | �S�@�� |
| ����20�N�R���� | 40.1�� | 42.2�� | 71.7�� |
| ����21�N�R���� | 41.1�� | �| | �| |
| �N�@�x | �l�� �i�l�j |
�������� �l���i�l�j |
���y�� �i���j |
������ | �_�W�r�� | ������ | |||
| �����l�� �i�l�j |
���y�� �i���j |
�����l�� �i�l�j |
���y�� �i���j |
�����l�� �i�l�j |
���y�� �i���j |
||||
| 20�N�R���� | 283,185 | 212,819 | 75.2 | 113,628 | 40.1 | 12,697 | 4.5 | 86,494 | 30.5 |
| 21�N�R���� | 282,569 | 216,629 | 76.7 | 116,136 | 41.1 | 12,672 | 4.5 | 87,821 | 31.1 |
| �S�~�̐V�ŏI�����ꌚ�ݒn�����@�@09.05.02 |
| �@�T���P���P�����A�R��̃��S���Ԃɕ��悵�A14�l�̋c�����S�~�̐V�ŏI�����ꌚ�ݒn�̌��n���@���s���܂����B��u�������̖���o�R�̃��[�g�ł��B�r���A�g���l���̗\��n��o�C�p�X�̌����n��Ȃǂł����Ԃ��Đ������A���^���s���܂����B�܂��A�n���̐��i���c��̕��X���Q������A���V��n��̘A����������炲���A������܂����B �@��ې[�������̂́A����c�������悯�̎P�͂Ȃ����ƐE���ɒT���������Ƃł��B�c�O�Ȃ��ƂɁA�R��̎Ԓ��ɎP�͂���܂���ł����B����ƈȌ�A���̋c���͉��Ԃ��邱�ƂȂ��A�����Ԃɕ��������Ă��܂��܂����B |
| �{�l�ƕی�҂ɖ��f�Ōl������@09.12.25 |
| �@�Îs�́A�{�l�ɂ��ی�҂ɂ����f�ŁA���Z�Q�N���ɑ�������j���̌l�������q���ɒ��Ă��܂��B����́u�ł���v�@���ɂ���čs���Ă���̂ł����A�u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�̂ł͂���܂���B���Ɂu���Ă��Ȃ��v�����̂͂�������܂��B �@��������m���̂Q�����̂����Ă����Ƃ��ĐV���L���ɂȂ�܂������A���邩�A���Ȃ����͎s���̔��f�ЂƂȂ̂ł��B�������Îs�́A�����̎s�������̎�����m��Ȃ����Ƃ��������ƂɁA�@�I�ɂ͖�育�����܂���A�Ƃ����ԓx�Œ𑱂��Ă��܂��B �@���q���͎s���������悤�ɁA�@���Ɋ�Â����g�D�ł͂���܂����A�ǂ������c�̂ł���A����Ɏ����̏������āA�悢�C������������̂ł͂���܂���B�l���̎�舵�����A����قǂ₩�܂����Ȃ��Ă��邲�����ł�����A����̂ł���Ζ{�l�ƕی�҂̗��������߂�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �������\�\�\�{���Ɂu������v���@���_�Â����͂Ȃ��� |
| �@�Îs�͍������Ĉȍ~�A�����ƌ����Ɓu������v����������悤�ɂȂ�܂����B�����č����O�ɍs���Ă����T�[�r�X�̔p�~�␅���̒ቺ���ł��o���A���X�Ɏ��s���Ă��܂��B �@���Ƃ����Îs���́u�x���v�͍����ɂ���āu�o�����v�Ɋi��������Ă��܂��܂����B����Ɂu�o�����v���R�ӏ��́u��^�v�i��g�c�A�_�ˁA�������j�Ƃ��́u�����v�ɕ����悤�Ƃ��Ă��܂��B����͂Q�O�O�X�N�x�i�����Q�P�N�x�j������{�\��ł��B�܂��A�������n��̗l�X�Ȓc�̂��x���Ă����⏕�����J�b�g����Ă��܂��i�\���l�����ɂ���Ă͑��̎����������j�B�����ق�s���Z���^�[�̗L�������s���Ă��܂��i���Îs�̌����ق͈ȑO����L���j�B�S���ōs���Ă������L��D��p�̏������Ȃ��Ȃ�܂����B �@���������L��������܂��A�Îs�͂Q�O�O�V�i�����P�X�j�N�x����Q�O�O�X�i�����Q�P�j�N�x�̂R�N�ԂŁA���z�T�T���~�ɂ̂ڂ�T�[�r�X�̒ቺ���߂������v���i�Îs�s�������v��j�j�\���Ă��܂��B �@�����ɍۂ��Ă̐�����ł́A�@�u����Љ�ɑΉ���������͂̊m�ہv�A�A�u�����ԎЉ�ɂȂ��Đ��������L�����Ă���v�A�B�u�������˂Ƃ��Ĉ�̊�������v�ƁA�O�̗��R�������č����̕K�v����������邾���ŁA�����܂��T�[�r�X���ቺ���邱�Ƃ͂����������ɂ��܂���ł����B�����͎w���Ō����ƁA���Îs�͂O�D�X�A���������͂O�D�Q�ł����B���̑��̒������O�D�R�Ƃ��O�D�S�Ƃ��������ł�������A�����͂��ቺ���邱�Ƃ͍����O���疾���������ɂ��ւ�炸�A�ł��B �@���������O�ɃT�[�r�X�ቺ��������Ă���A�����炭�s���͍����ɔ[�����Ȃ������ł��傤�B�Îs�������������A�Ƃ܂ł͌����܂��A�s�����ӎv���肷�邽�߂̏d�v�Ȕ��f�ޗ�����Ȃ������A��������ł����A�ƌ����Ă����_�ł��܂���B����ΐ����ӔC���ʂ����Ȃ������̂ł��B �@�������������d�v�Ȃ��Ƃ́A�{���ɒÎs�͍�����Ȃ̂��A�Ƃ����_�ł��B���_�Â������Ȃ������ƂȂ��A������Ƃ��ăT�[�r�X���̂ĂĂ���̂��Ƃ�����A�Ƃ��Ă��[�Ŏ҂Ƃ��Ă̎s���̔[���͓����܂���B�����ňȉ��Ɏ����l�����\�I�ȒÎs�̃��_�Â����s���������Ă݂����Ǝv���܂��B |
| ���_�Â����̐��X |
| �@�s�@�Z���^�[�p���X�ւ̔N�ԂR���~�̓����@�t �@�Z���^�[�p���X�̌o�c��@�ɂ��Ă͋ɂ߂ďd��Ȗ��ł��̂ŁA���̃y�[�W��݂��܂����A��������Q�Ƃ��ĉ������B �@�s�@�Ȃ�Ƒؔ[�W���~���̓��a�s���@�t �@�Z��V�z�����̑ݕt���Ƃ��W���~����ؔ[������܂��B�����̕��͂�����ƕԍς��Ă���̂ł����A�قƂ�Ǖԍς��Ă��Ȃ��l������A�ؔ[�z���傫���Ȃ��Ă��܂��B �@�s�c�Z��̉ƒ���ؔ[����Ɩ@�I��i�ɑi������̂ɁA���a��肪���ނƎs�͓r�[�Ɏ㍘�ɂȂ�̂ł��B�������A�e�n�ŕ�����������̗��ޓ��a���Ƃ̕s�����\�ʉ����Ă���i������������̒n�������ł���ޗǎs�����E�����j�Z�a���ŋ�����������Ă��������A���̒��ԏ�o�c��������Ă���������������n�̑g�D���s���o�����s���������A���������ŕ�����������̃}�[�N���f�����a�@�̕⏕���s�������A�����ĕ�����������̋��s�s�����E���𒆐S�ɋN�����������ȂǂȂǁj�A���a�s�����̂��̂��������K�v������܂��B �@���łɍ��̒i�K�ł́A��{�I�ɓ��a���͏I�������Ƃ̗���œ��a�Ɠ��ʑ[�u�@���p�~���A�c����ɂ͌ʂɈ�ʎ��ƂőΉ����Ă��܂��B�]���č��ɂ͓��a�s���͂���܂��A�������������Ɋ�@�������߂����a�^���c�̂͒n���ł̐����c���q���āu�^���v���������Ă���A�Îs�ł������Ȍ�A�R�O�N�̂ɋt�߂肵���ƐE���������قǂ̏�ԂɂȂ��Ă��܂��B �@������Ƃ����ĂW���~���̑ؔ[����u����킯�ɂ͂����܂���B���̒Îs�ɂƂ��ĂW���~�͍A����肪�o��قǂ̍����ł��B �@�s�@�����̑��������Z���^�[���ԏ�@�t �@���������Z���^�[�����̒��ԏ�́A�N�Ԗ�P�O�O�O���~�̒n����Ēn�傳��Îs����Ă��܂��B�Ƃ��낪�Îs�͂��̎ؒn�����ɖ����Ŗ��݂����Ă��܂��B����Ō��͕t�����E���w�Z�̒n��������������Ă���̂ł�����A�̒ʂ�Ȃ��b�ł��B �@�Îs�������Ō��ɑ݂��Ă���y�n�͑��ɂ�����܂��B�Ð����Z�̕~�n�ł��B���������ʂɒ��ݗ������炦�ΒÎs�̑傫�ȍ����ɂȂ�܂��B �@�s�@�D�݂̑����̑�T�[�r�X�@�t �@�э�̂Ȃ����܂����璆����`�ւ̗��q�D���^�s���Ă���͖̂��Ԋ�Ƃł����A�D�͒Îs�̏��L�ł��B������͂X���~���������Ă��܂��B���̑D��݂��Ă����āA�^�s���Ƃ����肢���Ă���̂ł����A�����Ȃ���A�D�݂̑����͂Q�ǂł킸�����S�U���~�ł��B �@������D�͔��������Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA���ʂ͂�����l�����݂����ɂȂ�܂��B���������̋��z�ł́A������X���~�ɒB����̂ɂP�U�O�N������܂��B�{���̋��z�A���̂P�O�{�ɂ���ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ̐����c��ŏo�Ă���قǂ̑�T�[�r�X�ł��B �@���̎��Ƃ��n�߂�ɂ������ĒÎs�́u�P�O�N�Ԃ͉^�s�𑱂���A�Ȃǂ̎O�̑O��������Ǝ҂ɏo���܂����B���̓��̈�Ɂu�Ԏ��̕�U�͂��Ȃ��v�Ƃ������̂�����܂����B�D�݂̑����𑊏�̂P���ɂ܂��Ă���Ă���̂́A������̐Ԏ���U�ł���A�Îs���s�����\���Ă���A��j���Đŋ��𓊓����Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@����݂̑��������A�P�O���N��̔����������ɂX���~���̐ŋ��𓊓����Ȃ��Ă����ނ̂ł��B |
| �@�s�@�Îs���g�ɂ���č��o���ꂽ������@�t |
| �@���̂悤�Ȑŋ��̃��_�Â��������Ă���ƁA��͂�u������v���Îs���g�����o���������ƌ��킴��܂���B�܂�ŋ��̎g�������Ԉ���Ă���̂ł����āA���R�ЊQ�̂悤�ɊO��������炳�ꂽ������ł͂���܂���B �@�s���݂̍����ς��Ȃ�����A����������ƁA�ŋ��̃��_�Â�������߂Ȃ�����A�u������v�͉������܂���B�c��ł́A���łɎs���̐��_�̗͂Ń��_�Â�������߂����Ⴊ�������Ă��܂��B�ς��邱�Ƃ͉\�ł��B �@�s�@�c���̊C�O���@�@�t �@�Îs�ł͕����Q�O�N�x���C�O���@�̗\�Z�����܂������A���_�̔ᔻ�Ƌc����ł̎��Ȃǂ̎咣�ɂ���āA�\�Z�����s���Ȃ����Ƃ����܂�܂����B����͎�����A�Ȍ�A�ŋ��ł̊C�O���@�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �@�s�@����������̍팸�@�t �@�Îs�͋c���P�l������A���T���~�̐���������\�Z������Ă��܂��i�g��Ȃ��������͕Ԋ҂��܂��j�B��������N�Q�O�O�V�N�x�͂P���~��ԏサ�Ă`�d�c�i���ד���A�d�C�V���b�N�j�̐ݒu�Ɏg���܂����B�Q�O�O�W�N�x�����l�̑[�u������A�ۈ牀�̒n�k�ɂ��K���X�̔�U�h�~�t�B�����Ɏg���܂��B �@���́A���߂Ĕ������A�Ǝ咣���Ă���̂ł����A�c��S�̂Ƃ��Ă͂P���~�팸�����x�ł����B�����A�Îs�̐���������͌������ݒn�̒��ł͉�����R�Ԗڂɏ��Ȃ����z�ł�����A���̒��ł̂P���~�팸�͂���Ȃ�ɕ]�����ׂ����ȁA�Ƃ��v���Ă��܂��B�Ȃ��A�Îs�̏ꍇ�͂��ׂĂ̎x�o�ɗ̎�����Y�t���Č��J���Ă���A�c����ǂɗ��Ă�����������ł��{�����邱�Ƃ��ł��܂��B |
| �g�b�v�y�[�W�ɖ߂� |
| ���T�P�S�|�O�P�P�S�@�Îs��g�c���Q�V�X�O�@�s�����D�e�����@�O�T�X�|�Q�P�P�|�O�P�Q�U ���[���@hpvqg2qv@zc.ztv.ne.jp |